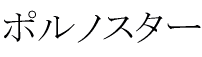 |
||
|
他人の寝顔を見るのは酷く久しぶりのような気がした。何年ぶりだろうと考えることも馬鹿らしく、ゆっくり身体を起こす。慣れないベッドで眠るのは激しく疲労してしまう。これだから自分は旅行にも行けないのだ。 すぐ真横には祐正の寝顔がある。すでに見慣れてしまった感のある横顔に、胸が苦くなった。 つまり昨晩、この腕は彼を抱き締めるだけに留まらなかった。額から頬へ、頬から鼻先へ、それから唇へ。いっそ稚拙だと笑ってしまえるくらい子どもじみた口付けに、彼はなぜか抗わなかった。繰り返されるやわらかい口付けに彼の喉が鳴って、それがじれったさへの抗議だと気付いたのも、随分時間がすぎてからだった。首に伸ばされた腕が、縋りつくための力だと気付いたのも。 何かを言おうとして開きかけた唇は、結局なんの言葉も選べず、閉ざしてしまう。代わりに、抱き締めた身体を降ろし、そっと床に押し倒しても、彼から抗う力は返って来なかった。 言葉など最初から足りてはいないから、今更埋め合わせる努力などしない。足りないのなら足りないまま、擦れ違うなら擦れ違うまま、無様な摩擦だけを起こしていればいい。 言葉は無力だ。 吐息はやがて啜り泣くように色づいて、頑ななまでに言葉を発しなかった唇が「ゆるして」と懇願した。その瞬間、胸の痛みは容易く欲情に変わる。それを誰も――彼も、嘲わなかった。 男の身体は正直だなんて言葉を、酷すぎて今は言えやしない。 彼を悲しいと思うには、自分の掌はやはり無力であった。 せめてこの瞼が開かなければ、もう二度と悲しくはならないだろうと、そんなことばかりを考えている。 聴こえてくる寝息はただ穏やかで、涙が出そうになった。 もう二度と開かなければ。戦うことも、意味も。 けれど何もかもを裏切って、祐正の瞼が静かに持ち上げられていく。 覚醒が近い。――ああ、朝だ。 「あんた、しつこいんだけど」 ちくしょう、寝過ごした。そう忌々しげに呟いたあと、続けて祐正は世間話のひとつのように軽い口調で言い捨てる。それが朝の第一声かと思えば頭が痛くなるような気もしたが、敢えて、 「……そうですか」 従順しい返事を返すことにした。 「すみません。以後気をつけます」 次いで、どうでもいいことのように謝ると、祐正はどこか不満げに鼻を鳴らしてみせる。しかしそれ以上は何も言わず、黙ったまま床の上に脱ぎ散らかした衣類を拾い上げていくと、何の余韻も見せずにだらしなくシャツを肩だけに引っ掛けた。果たして「以後」なんてあるだろうかとぼんやり思う。彼と自分との間には。――二度目のセックスがあったこと自体が予想外だというのに。 「……北沢さん、」 「なに?」 「これからどうするつもりなんです。インド行くんですか」 「行こうかな、来週くらいから。仕事なくなっちまったし。おまえも一緒に来るか?」 ふいに見せた祐正の笑みは、意外なほどに明るい笑顔だった。頭の切り替えが早いのだろうか、と思う。それなら少しは救われる。 「行きません、俺は学生です。貧乏暇なしなんですよ、あなたと違って。……あなただって仕事がなかったら、旅行に行く金もないんじゃないんですか?」 「それがな、金はあるんだ。じーさんが遺してくれたおかげで。若いころ金がなくて自分が苦労してたから、俺に同じ思いさせたくねーってたんまり遺してくれてんの。馬鹿だよな、苦労しなきゃ撮れねえ写真だってあんのに」 「じーさん?」 即ち、彼の祖父であり業界で名を馳せたカメラマンでもある北沢常保のことだろう。祖父から遺された遺産のおかげで、仕事が干されたとしても一応生活はできるらしい。そのことに安心しながら、ばかばかしい、と亮はひとりかぶりを振った。何だって、自分がこの人の心配なんて。 「……いい身分なのはどっちですか」 亮の皮肉にも、祐正はただ笑っていた。 からからと響く笑い声は、不思議と心地良く胸を揺るがした。 そしてすぐに、先刻の自分の考えが馬鹿らしくなる。目を開かなければいいなんて、とんだ勘違いだった。起き抜けの思考のせいで、きっと、どうかしていたのだろう。 目を開いてファインダーを覗く、カメラとその腕ひとつで戦う、その姿こそが彼を彼として生かしている、その才能こそが、この人そのものだった。 「――インド?」 宮坂沙希は綺麗に上がった眉をきつく顰め、ひどく怪訝そうに呟いた。祐正の今後スケジュールを知っているかと尋ねられ、どうやらインドに行くようだと答えた亮への反応がこれである。 「どうしてまた、インドなんかに……仕事?」 不思議そうに聞き返されても、祐正のことなど相も変わらず何ひとつ理解できていない亮には、納得のいく説明などできない。 「いえ、プライベートみたいでしたよ。確かマンドゥという小さな町で、……あぁ、そうだ、バオパブの木が唯一生えているとかいうところで」 「……亮。いいのよ、そんな説明はしなくても。あぁ、頭が痛い……」 宮坂は憂鬱そうに呟き、額を押えた。 「それで、彼が出かけるのはいつからいつまで?」 「来週くらいから行くつもりだと聞きました。……半月くらいは帰ってくるつもりがないと言っていたような……」 「半月? それはまた季節のずれた長期休暇ね……」 宮坂はそれきり、何事かを考え込むように唇を引き結び、暫くの沈黙を保った。この広々とした社長室に相応しい女社長の顔付きである。今の彼女の頭の中には、ビジネスの話しか存在しないということだ。 「……引き止めて」 「……は?」 「北沢を引き止めておいて。丁度彼を使おうと思っていたグラビア企画が始まる時期とかぶってるのよ、彼がインドに行く予定の期間が」 「いや、引き止めるって……」 それは些か難しいものがあるのではないか、と声には出さず反論する。何しろ自分如きが祐正の行動を規制する権利などありもしなければ理由もない。もちろん彼が自分のいうことを聞き入れる可能性など皆無に等しいのだ。 「もう時間もないわね。丁度いいわ。亮、北沢に仕事の約束を取り付けておいてくれないかしら?」 「……俺が、ですか?」 「ええ、来月の頭から撮影を開始するグラビア企画に北沢祐正の手を借りたいの。それを伝えておいてちょうだい。出版社との打ち合わせもあるからできるだけ早めに返事がほしいわ」 「って、沙希さん、ちょっと待ってください。どうして俺が……」 自分が頭を下げたところで、祐正が大人しく仕事を引き受けるとは思えない。そう言いかけたところで、思考が停止した。違う、そうじゃない。これは多分、あの人が待ち望んでいたことだ。 「もう北沢とはだいぶ親密になれたんでしょう? 情でもなんでも使って、ぜったいに頷かせて」 頭を下げても、下げなくても。 祐正は、何かしらの形で、何かしらの理由を以って、宮坂との繋がりを求めている。 ――それは、もしかしたら。 突然浮かび上がった疑問と昨晩見せ付けられた現実とがリンクする前に、亮は頷いて見せる。それは、あまりにもリアリティを伴わない考えだった。 案の定、祐正は二つ返事で亮が伝えた仕事の依頼を引き受けた。詳しい仕事の内容など訊きもせず、「わかった」とだけ告げた電話越しの彼は、もしかしたら予想通りの展開にほくそ笑んでいたのかもしれない。それほどに祐正が宮坂との繋がりを求めるのは何故なのか。答えは出ないうちに、祐正はその足で事務所に訪れていた。 「ねえ、今応接室にいるのって、あの北沢さん……?」 まさか仕事の話をしている宮坂と祐正の間に割り込むわけにもいかず、成り行きを気にしながらも事務所内をうろうろしていた亮に小声で話し掛けてきたのは、社長秘書の吉見だった。 「吉見さん、知ってるの?」 「名前だけは。よく社長が話に出すの、聞いてたもん」 去年大学を卒業したばかりで、歳の近さから亮も気安く口を利くことができる彼女は、三人いる社長秘書の中では新人に数えられ、茶汲みなどの雑用に回されることが多いらしい。今も来客用の茶をトレイに載せ、祐正を迎えた応接室へと向かっている最中だった。 「本人見たのははじめて。思ってたよりずっと若かったわ」 「吉見さんと同じ歳くらいじゃないのかな」 「そうなの? じゃあ社長の息子さんと同じくらいの歳?」 「ああ、……そういうことになるのかな」 宮坂沙希には、一応二人の息子が存在している。二人とも旦那の連れ子で、長男は亮より二、三年長だと聞いているから、吉見の言葉は正しいのだろう。 「社長の息子さんもカメラマンよね。北沢さんと知り合いだったりするのかな」 一人目の息子――長男は、確か正人という名前だった。やはり祐正と同じスタジオカメラマンで、この事務所をうろうろしている姿を何度か見かけている。宮坂の夫婦仲はとうに冷め切っているが、血の繋がりのない親子はそこそこに仲良くやっているらしい。 「俺は何も聞いていないけど、もしかしたらそうかもしれないね。広く見えて狭い世界だから」 さり気ない仕草で吉見からトレイを受け取ると、不思議そうな顔をする彼女に小さく笑い、 「北沢さんとは知り合いだから、俺がお茶を運ばせてもらってもいいかな」 もっともらしい言い訳を、彼女は疑うことすらしなかった。応接室の前をうろつくことしかできなかった自分にでも、言い訳さえ作ることが叶えば祐正と沙希の話を伺える。 「じゃあお願いね」 吉見はそれだけ告げるとトレイを亮に任せ、仕事場へと戻って行く。彼女の背中を見送って、亮は厳かな手付きでドアをノックした。 この扉の向こうでは、祐正と宮坂沙希が対面しているのだ。一体どんな会話がかわされているのか。恐らくは仕事の話でしかないのだろうが、好奇の虫は収まらない。 返事が返るのを待ち、ゆっくりと扉を開ける。目に飛び込んできた光景は、亮の予想を裏切っていた。 「――女が怖いって思うのはあんたみたいな人を見たときだよな。おばさん、今年で幾つだよ」 「誉め言葉として受け取っておくわ。――ああ、亮。ありがとう」 堅苦しい雰囲気もなく、さりとて険悪そうな重たい空気もなく、彼らは至って呑気に談笑していた。亮の姿に気付いた沙希が、視線だけを向けて小さく微笑む。 「……いえ、失礼します」 ――「おばさん」? 混乱する思考をないもののように振る舞いながら、亮は静かにカップをテーブルに並べる。自分の耳がおかしくなっていないのなら、さっき祐正は宮坂沙希をおばさん呼ばわりしてみせたのだ。しかも相当に親しげな口調で会話を続けている。――ということは。 彼らは、亮が介入するずっと以前から、顔見知りであった可能性がある、ということだ。 益々訳が判らない。元々顔見知りであるのなら、何故わざわざ自分を介したりしたのだ。 祐正は一度も自分を見ようとはせず、ただ真っ直ぐに沙希を見つめ会話を続ける。どうやら話題は、仕事に関する話だけではないらしい。 部屋を出たあと、閉じた扉に背を凭れ亮は不可解な感覚に首を捻った。 元から知り合いであるならば、あの態度は別段不思議なものでも何でもない。それでもどうしても付き纏う違和感に、応接室を出てからも暫く亮の混乱は収まらなかった。 それから祐正と沙希が応接室から出てくるまでに、然程時間は要さなかった。恐らく小一時間と言った程度だろう。沙希は元より多忙な人間だし、事務所の社長とカメラマンの間に、込み入った話がそれほど多くあるはずもない。 「何、おまえずっとそこで待ってたの」 応接室を出て、真っ直ぐにエレベーターへ向かおうとしていた祐正は、その横に腕を組み佇んでいた亮の姿に気付くと、何の拘りも見せずに笑いかけてくる。まるで透明人間のように存在を無視されていた応接室での出来事は何だったのだろうと、混乱が混乱を呼んだ。 「早かったですね。仕事の話、済んだんですか」 「そんなに話すこともねえもん。今度事務所の子と会わせるからってスケジュール訊かれたのと、出版社との打ち合わせの日程を確認しただけだ。小山みなみって女、知ってる?」 「知ってますよ。今売り出してる途中のグラビアアイドルでしょう、うちの。宮坂社長が随分熱心でしたから、売れるんじゃないんですか。そのうち」 ボタンを押し、上昇してくるエレベーターを待つ間に聞かされた名前は、この事務所に所属するグラビア系のモデルのものだった。元々はファッション誌の出らしいが、優れた容姿とプロポーションからグラビアアイドルに転向した。要はその女が祐正の手によって売り出されることになるのだろう。 「そのうちってなんだよ、興味ねえの? 一応仕事仲間だろ」 「興味というか……あまり」 「なあ、そいつ胸デカい?」 「……さあ」 曖昧に質問をはぐらかしているうちに、エレベーターが階に辿り付く。共に乗り込んだ亮に向かって、「おまえも来るの?」と祐正は不思議そうに視線を上げた。 「ご一緒しますよ」 どうせ今日は用事もないと軽い調子で応えてから、一階のボタンを押す。 「小山みなみの胸が大きいと、何かあなたが得をすることでもあるんですか?」 「いや得っていうか。ないよりはあったほうがいいだろ」 「……巨乳が好きでしたか。それは知らなかった。社長に伝えておきます。北川祐正の接待には巨乳の女がいいらしいって」 「……なんでそんなに噛み付くんだよ」 怪訝そうに片眉を上げ、祐正は、睨むというには弱すぎる視線を、そっと亮に向けた。不思議と胸が騒いで、何も言葉が浮かんでこない。 静かに下降していく箱の中で、小さく祐正が呟いた。 「女は、抱かねーよ。……今までだって、宮坂からじゃなくても女なら幾らも宛がわれてる」 答えを黙殺し、カウントダウンのように点滅する数字を見つめながら、その呟きを聞く。 「仕事取るための女と寝たって、後味が悪いだけだ」 「……ならどうして俺と寝たんですか」 「自分が後味悪い思いするよりは、相手に味合わせたほうがマシだって思ったからだよ。不思議だよな、セックスってのは本当なら対等なはずなんだ。だけど、あんときおまえ、俺に謝っただろ。――申し訳なさで、おまえはもう俺に頭が上がらないんだ」 そうだろう。笑みを浮かべて、祐正が真っ直ぐに視線を寄越す。 正しい。反発したい心の片隅で亮は思う。祐正の言葉は、正しく的確に己の真実を突いていた。最初の日、そして二度目の日も。自分はどこか、彼に対する後ろめたさを抱いていた。抱くか抱かれるか、ただそれだけの関係の違いで生まれる僅かな罪悪感を、彼は明確に知っている。 生まれるはずのないものを、確かに掌中に掴んでいる。 「あんた、一回死んだらどうですか」 無性に、腹が立った。その感情のまま告げた言葉に、祐正がくぐもった声で笑う。 「――気が向いたらな」 女とは寝ない、宣言した通り、恐らく彼は女性と関係を持ったことがないのだろう。少なくとも、あの事件以後はそうであるように思えた。 「北沢祐正はゲイだそうですよ」 「――は?」 「あんたと寝てこいと社長に言われたとき、そう教えられました」 ほんの一瞬、呆けるように目を見開いた祐正は、すぐに弾かれたように笑い出した。他人事ではないだろうに、おかしくて堪らないとでもいうように笑いながら腹を抱える始末だ。 「ハハハッ、そりゃいいな。道理で最近誘いがぱったり止んだわけだ! ……それで、おまえが俺んとこに来たのか」 「うちの事務所には俺以上の男前がいないからだそうです。これは完全にあの人の身内びいきでしょうが」 「ああ、そういえばおまえあの女のヒモだったっけ――」 ふいに笑いを止め、くしゃりと長い髪を掻き上げながら、彼はまるで独り言のように囁いた。舌打ちのように小さなそれは、うっかりすると聞き逃してしまいそうになるほど微かに亮の耳を打つ。 「――忘れそうになる」 その言葉の意味を図り取れないうちに、エレベーターが音を立てて到着を告げた。 「北沢さ……」 呼び止める前に、小さすぎた言葉の意味を尋ねるよりも早く、祐正はエレベーターを降りてしまう。今のはまるで、亮を普通の友人だと――何の利害も含まない、やさしい関係なのだと勘違いしそうになると告げているようで。 それが、彼の寂しさを露呈しているようでもあって、無性に胸が痛くなった。 先を行く祐正が、自動ドアの手前で、丁度ビルに入ってきた男と肩がぶつかり合ったのが見える。すぐに追いついた亮の横で、「すいません、」と面倒くさそうに謝った祐正は、男を見上げたところで動きを止めた。 「――祐正? おまえ、なんでこんなとこに、」 サングラスを僅かに下げ、驚きに目を瞠る男を見て、祐正は更に驚愕を見せる。 「……正人」 「久しぶりだな。……おまえがそんなに驚くことないだろ。お袋の事務所なんだから、俺がいたって不思議じゃないんだから。驚きたいのはこっちだよ」 苦笑と少しの微笑みを見せ、男は肩を竦めて見せた。亮と並ぶ長身であるにも関わらず威圧感がないのは、滲み出るような剽軽さのせいだろうか。驚いた、と明るく笑って見せる男は、短めに刈った髪を掻き、ふいに亮へ視線を投げた。 「ああ、確かお袋の……」 「……お久しぶりです」 視線を受け、亮は小さく頭を下げる。見かけたことは数多くあれども、実際に言葉を交わした回数は少ない。彼は、宮坂沙希の息子である。つまりは宮坂正人だ。複雑すぎる関係のせいで、少なくとも気安く口を利ける間柄ではなかった。 「お袋が世話になってるな。あの人、働きすぎだからたまには君からも注意してやってくれ」 しかし、血は繋がらないとは言っても母親の愛人である亮に対して、正人は何の拘りも見せない。この辺りはさばさばとした親子関係だ。父親のほうも若い女と好き勝手やっているらしく、子どもからしてみれば、呆れるを通り越して他人事も同然なのかもしれない。 「それで祐正、こんなところにいるってことは、とうとうお袋に捕まっちまったのか。前からおまえに仕事頼みたいってうわ言みたいに言ってたからな、あの人」 親しげに話し掛ける様子を見れば、彼と北沢祐正はどうやら旧知の仲らしい。ということは、やはり宮坂沙希と祐正は元々顔見知りであったと考えても間違いはない。 「捕まったっていえば、まあそういうことになんのかな――」 祐正はふいに視線を亮へ流す。ほんの一瞬、亮の顔を意味ありげに見つめたあと、幾分高い位置にある正人の顔を仰ぎ、微笑んだ。 「惚れたヤツの頼みなら聞いてやりたいだろ?」 この言葉に、心臓が止まりかけたのは亮だった。正人は驚いているのか、それとも感心しているのか、どちらともつかない表情で「へえ、」と亮を眺めている。 「ハマったの?」 「そう。だからママに言っといてよ。俺にコイツちょうだいって」 「そりゃあどうかなあ……。君、ええと片山君だったかな。もうあの人と二年になるだろ? それだけ長く続いてるってことは、あの人も手放すつもりはないんじゃないか」 正人は笑いながら亮の肩に手を置き、「モテる男は大変だなあ、」と気楽に揶揄う。亮は答えるどころではない。今も浮かべる愛想笑いは、引き攣ってはいないだろうか。 「そういやお前が俺の名前を出してくれた仕事、こないだ終わったぜ。北沢祐正が突然抜けたおかげで現場は大混乱したけど、何とか落ち着いた」 続けて正人が告げた言葉に、一瞬亮は思考を奪われる。 「あの、それって……」 もしかして、と控えめに話を遮ると、正人が思い出したように頷き、亮に指を差した。 「ああ、そういえば君も参加してたよな。俺が加わったときにはもう君は終わってたみたいだね、お袋が溺愛してる君を撮れなくて残念だった」 「いえ、まだ終わったわけじゃ…俺はまだCFの撮影が残ってるんです」 やはり、そうなのか。ついこの間、祐正が放棄した仕事の後釜に、彼が収まったというわけである。祐正が推薦したカメラマンが撮影を続行しているとは聞いていた。祐正が推薦するくらいなら、彼も相当の腕なのだろう、と亮は推測するしかない。 「こいつ、何かと自分の仕事を俺に押し付けやがるんだ。自分勝手にも程があるだろ?」 同意を求めるように、正人が笑いながら首を傾げる。真実を知っているだけに、易々と頷けるはずのない亮は、静かな笑みだけでそれに応えた。 「……俺の抜けた穴を埋められるのは、おまえだけだ」 ふいに、ひどく静かな声で祐正が告げた。 「おまえしかいない」 真摯な響きを以って言い切った祐正に、ふっと笑みを零したのは正人だった。 「……おまえの口からそんな科白が出てくるとは思わなかったな」 正人は唇を歪めて、皮肉っぽい笑みを見せる。これまでの朗らかなものとは一転し、苦々しさを含めた笑みに、違和感を抱く。今まで親しげだった雰囲気が、まるで触れてはならないものに触れたかのように、一気に変わってしまった。 「俺は昔っから、おまえの劣化コピーでしかないんだよ。――おまえが一番知ってただろう、祐正」 祐正を追い越した正人の足音は遠ざかり、やがてエレベーターに消える。微か機械音を響かせて戸が閉まったあとに、祐正は小さく何かを呟いた。 「……北沢さん?」 「……そんなこと、一度も……思ったことなんか、ない」 もう届かない言葉を、まるで、祈るかのように。 「友達だったんだ」 定期的な電車の揺れに身を任せる。流れていく景色を映すガラスに額を押し当てながらも、彼はどの景色も見ていなかった。 「高校時代の友達でさ。よく一緒に色んなコンクールに出展したり、知らないとこに旅行行って写真ばっか撮ってたりしてたよ。バカばっかやってたな」 「……やっぱり、宮坂社長とも知り合いだったんですね」 「そんなに深く知ってるわけでもないよ。あいつの自宅にも遊び行ったりしてたからな。金持ちの坊ちゃんってことは知ってたけど、あいつの母親と父親がそれぞれ社長やってるなんて知らなかったし。顔くらいだ、知ってたのは」 ガタン、ゴトン、と規則的な音が耳を打つ。かろうじて聞き取れるほどの小さな声で、祐正は他人事のように淡々と話してきかせた。 「おまえ、紫竜賞って知ってるか?」 「……いえ」 「柏崎紫門、木野竜三。神様みたいな二人の写真家が中心になって設けた賞で、新人カメラマンの登竜門みたいな賞だ。この賞さえ取れば、名前は一気に広まるし仕事も舞い込んでくるから、誰でも最初は憧れる。俺も正人も憧れた。これに出展しようって話をしたのは、卒業の記念みたいなノリだったんだよ」 車を呼ぼうとした亮を止め、電車で帰ることを望んだのは祐正だった。たまにはゆっくり歩いてみたいのだと笑った。学生時代はよく使っていた電車を、或いは懐かしみたかったのかもしれない。 「……夢みたいだった。俺の手に、それが転がり込んできたのは」 ふっと両手を広げ、顔を俯かせたまま祐正はその掌を見つめる。 「俺は、薄汚い手で、神様を掴んじまった。――だからだ」 その話なら、少しだけ沙希に聞いている。祐正は、最年少で新人カメラマンの登竜門と呼ばれる賞を受賞した。きれいなものをより美しく映し出す掌で、己に与えられた才能で、彼は栄光を掴んだのだ。 「一生涯だと思っていた親友をなくしたのも、ライバルをなくしたのも」 なのに彼は、それを夢だという。自分には相応しくない夢なのだと。 「正人と俺は、撮るものが良く似てたんだ。俺はそれが嬉しかった。同じものを綺麗だと感じて、同じものを同じように表現できるくらい、感性が近い人間が傍にいるのが、本当に嬉しかった。――本当、なんだ」 俯いた横顔に、長い髪が降りかかる。それを微かに揺らしながら、くぐもった声で祐正は続けた。 「似てるからこそ、俺とあいつは互いを高め合ってた。これからもずっとそうなんだと思ってた。なのに正人は、俺から、離れていった。下手に撮るもんが似てたせいで、俺が正人の将来をブチ壊したんだ」 ――そうだろうか。流れるように紡がれる言葉を受け止めながら、考える。互いを高めあっていた、切磋琢磨していたのだと祐正が信じられていたのは、それこそ彼が正人の才能を上回っていたからなのではないだろうか。それが紫竜賞を受賞したという揺ぎ無い実績を持って、誰の目にも明らかになってしまった。 「あいつは、俺の劣化コピーなんて言われ始めて、……俺の名前が先に出たせいで、あいつが苦労したっていうんなら……いいんだ。俺なんかのせいであいつの才能に誰も気付いてやれないっていうんなら、」 彼は、突出した才能の故に、友人さえも失った。 「俺は、よかったんだ」 愛を囁くように、祐正は静かな声で続ける。 「縛られたままでも――身動きが取れないままでも、よかった」 ――そう、それは、愛でも囁くように。 自分が正人の障害になっているのなら、あの写真を理由にして己の前途が塞がれたままでも構わない。自分が動かないことで彼が脚光を浴びるのなら、それでいい、と。 「よくありませんよ、少なくとも俺は」 視線を落としたその掌は、思うよりも無骨で、それでいて繊細に動くことを知っている。 その掌が生み出すものを、瞳が見つめるものを。自分は、知っている。 「――俺は、あなたに撮ってもらってよかったと思ってる」 そう思うことが、告げることが、彼の力にならないか。彼の、何かの力に、ならないか。 既に闇に染まった暗い風景を見つめながら、彼は泣きたいような顔で、ただ笑っていた。 |
||