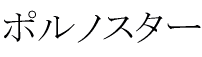 |
||
|
触れたときはむしろその柔らかさに驚いた。それほど体格は違わないはずの男の身体は想像していたようなものではなく、丁度よく腕の中に収まる。少しも痛くない、硬くもない、ただひたすらに柔らかいだけの肉にそっと包み込まれる。だらしのない、淫猥な動きで咀嚼されて、このまま身体ごと呑み込まれてしまうと思ったときにはただの男に成り下がっていた。目が覚めて、白い背中を向けられているのに気付いた瞬間、体中から血の気が引く。だから嫌だったんだ。本当に。こんな獣染みた衝動は、嫌だった。 「セックス、嫌いなんだろ」 面白そうに笑う横顔が酷く憎たらしくて、敢えて答えようとはせず、無言を貫き通す。無性に煙草がほしくなり、しかしこの場面でそんなものを口にするのは厭味すぎるかと我慢した。動くのも億劫だと言わんばかりに壁に背を凭れ、引き寄せたシーツを抱き込んでいる。長い横髪から覗く眠たそうな瞳は思ったよりも幼い。 「――別に」 それでも自分より一つか二つ年長であるはずの男は子供のように笑って、「俺のパンツ取ってくれる?」無遠慮に指図した。言われた通り、床に落ちた衣類を拾い上げて投げ付ける。受け取ったパンツのポケットを漁り、彼はライターと煙草を取り出した。 「ヤってたら判るんだよ、そんくらい。何我慢してんの。嫌々ヤってもらったって面白くないんだけどこっちも」 「煙草、一本貰えますか」 「吸うの? おまえまだ二十歳前だろ」 「いえ、二十一歳です」 「あぁ、そう。……おッかしいな、十九だか二十歳だかって聞いたんだけど。今、大学二年じゃないの?」 煙草を挟んだ指で、彼は頭を掻いた。それは決して、彼の記憶違いではない。 「俺、一浪してるんで」 「あぁ、だから二年で二十一? 誕生日早いのな」 雑談めいた話など、こんな朝には相応しくない。しかしそう感じているのは自分のほうだけかもしれず、余りにも気の抜けた相手の態度に、面食らってしまいそうになった。朝っぱらからこんな、どうでもいいような、詰まらない話なんて。 「いい身体してんな。なんかスポーツやってた? 俺陸上やってた人知ってんだけど、あの人はこんなに筋肉付いてなかったもんな」 ふいに、煙草を持つ手とは逆の指で、彼が手を伸ばしてきた。丁度腕を伸ばせば届く距離の背中を、指先で突付く。つ、と柔らかく爪先でなぞった肌には、きっと昨晩、彼自身が残した爪痕でもあるに違いない。 「バスケなら、中高で少しかじった程度ですけどやってましたよ。陸上なら筋肉の付き方が違うでしょう、種目にもよるけど……」 「何つってたっけな。短距離だっけ」 まるで労わるようなやさしさで、彼はほんの少しだけ沁みる爪痕を指の腹で撫でた。そっと。不似合いなやさしさで。 「俺にも判ることがありますよ」 もう目論見は完全に知られてしまった。既に相手の掌で転がっていることは自覚しているが、それでもカードは出来るだけ多いほうがいい。どんなに小さくとも、どんなに卑小でも。 何、とゆるく首を傾げた男の無防備な表情に、疑いたくなる。様々な思惑が絡み合って出会ったはずなのに。まるでこの時間が準備された運命の舞台なのだと勘違いしそうになる。 「あんた、男相手にするの初めてじゃなかったでしょう。でも、俺が触る度に緊張して震えてた。怖かった? 嫌なことでも思い出して――」 全くの、根拠のない言葉でしかない。なのに初めて男の表情が崩れる。ひどく軽い、取ってつけて無理矢理張り付けたような笑顔を浮かべていた顔が、初めて自分の目の前で崩れて、凍り付いて、唖然とした色を帯びていくのを、どこか遠くで見ていた。 「――レイプでもされたんですか」 「――だったら何だっつーの」 指先の震えが煙草に伝わり、真っ直ぐに立ち上るはずの紫煙を歪ませる。動揺は真実を垣間見せたかのようだった。 「可哀想つって頭撫でて抱き締めてくれんの? ――ばッかじゃねーの」 「そんなことしませんよ。気持ち悪い」 「どうでもいいけど、おまえモデル向いてないよ。止めたら?」 いきなり転換された話題を切り付けられ、ほんの一瞬言葉に詰まる。体勢を立て直そうとしているのか彼は返事がないことも一向に気にせず、言葉を続けた。 「モデルっつーかああいう仕事は向いてない。おまえの空気が強すぎて、全然商品の宣伝になるような写真撮れねーもん。主役がおまえに負ける」 「……そういうもんですか」 「そういうもんだよ、俺がどんだけ苦労したと思ってんの。おまえに負けねーくらい商品活かした写真撮るの。まして今回はおまえを売るんじゃなくて商品を売るための仕事だろ。下手したらモデル降板もあったかもな」 「あなたなら撮れるでしょう。俺が幾ら不向きなモデルでも」 そうでなければ天才の名が泣く。言わず、胸の中でだけ続けた言葉を読み取ったように、彼は薄く笑った。彼ほどに恵まれたカメラマンは早々いない。スタジオ入りの時間を大幅に遅れてやってきた上、それが容易に許されるような立場にある、二十代前半の若手カメラマンなど、彼以外においては。 「おまえんとこの社長も、もうちょっと回す仕事考えりゃいいのに」 「正式に契約してるわけじゃないですから。俺は文句なんて言えません」 「いいご身分で」 面白くなさそうに言い捨てると、彼は添え付けの灰皿に短くなった煙草を押し付ける。すぐに火の消えた吸殻を灰皿に落とすと、彼はシーツに包まり再び背を向けた。もう一度眠ってしまうつもりなのかもしれない。 「今日は仕事はないんですか」 「夜。……そういやおまえ学校は?」 「さあ……」 「……ほんっといい身分だよな。ムカつくくらい」 お互い様だと胸のうちで笑い、腰を上げた。このまま学校へ向かうとしても、シャワーを浴びるくらいの時間ならあるだろう。結局吸わず仕舞いだった煙草を一度ローテーブルに置き、気だるい身体を引きずりながら歩く。もう彼の背中は振り返らなかった。 自分がいい身分であることを、亮は十分承知していた。片山亮という人間が学生であることに対して使われた言葉ではない。芸能プロダクションの女社長に見初められ、言ってしまえばヒモ同然の生活を送っていることに対して向けられた、ただの嘲笑だ。そのことに対して、亮は何の感慨も抱かない。悔しいとも情けないとも思わず、ただ流されるように、気が付けば現在の位置に収まってしまっていた。 昨日知り合ったばかりのカメラマンに言った通り、亮は正式に契約を結んだ事務所の商品ではないが、時折、小さな仕事を宛がわれる。例えば通販のカタログに載るようなものから、紳士服のチラシ広告に載るような小さな仕事まで、やれと言われれば大人しく従った。それくらいの仕事でも宛てていなければ、若い男を囲っている社長の体裁が悪いのだろう。 ただ今回の仕事だけは、いつもと事情が違っている。既に名の通っている貴金属・アクセサリーを取り扱う大企業が若手デザイナーを援助独立させ、新ブランドを打ち出した。その筆頭となる商品の広告モデルとして、亮は生温い檻から狩り出されたのだ。業界の注目度も高いこの仕事を、喉から手が出るほど欲しがっているモデルなど、幾らでもいるだろう。 一抹の不安を抱きながら向かったスタジオに、一時間半遅れで到着したカメラマンが、彼、北沢祐正だった。 『いい仕事なのよ』 実年齢よりもずっと若々しい唇を、薄く上げて笑った女の顔が蘇る。 『撮影は北沢祐正だし、商品的にも話題性が十分でしょう。北沢祐正が撮るってだけでもすごいことなのに、うちにとっても充分価値のある仕事だわ』 正直に言えば、その名前に聞き覚えがなかった。それほど業界に興味のない亮を笑って、社長は上機嫌に『天才よ』と告げた。 『確か祖父が有名なカメラマンで、最初はスタジオカメラマンじゃなかったみたいだけど、ここ何年かで趣旨替えしたみたいね』 祖父の名の影響もあってか期待はされていたカメラマンだったらしいが、新人カメラマンの登竜門と呼ばれる賞を最年少で受賞してからというもの、目に見えて地位が確立されたのだと社長は続けた。 『彼は余り仕事をしないことで有名なのよ。一年の殆どは外国を飛び回って遊んでるって噂でね、気が向いたときにしか撮らないの』 嫌なやつだと思ったことを覚えている。甘い状況に胡座を掻き、与えられた仕事をしないなんて傲慢にもほどがある。自分のことは棚に上げ、そのとき亮は、心から北沢祐正を嫌悪した。 『だから北沢祐正の名前があるだけでも、充分すぎるほどなの。このまま北沢がうちを気に入って、仕事を引き受けてくれるようになればいいんだけど……』 だから失礼のないように気をつけてね、と笑顔で付け加えられ、亮は益々困惑した。 『……それなら、俺じゃなくても』 『いいえ、あなたじゃないと駄目。だってあなた以上の男前がうちにはいないんだから仕方ないじゃない』 どういう意味だと眉を寄せた亮に向かって、社長は信じられない言葉をあっさりと叩き付けた。北沢祐正は、ゲイなのよ。 シャワーを浴び、部屋に戻ると、変わらない姿勢で横になった祐正の背中が目についた。寝入ってしまっているのかもしれない。 眠りに就いた人間の傍にいることに、多少の居心地の悪さを感じながら、ベッドを軋ませて腰を下ろす。吸わず終いだった煙草に手を伸ばして、同じくテーブルに置かれたライターを拾い上げる。 亮は、社長に言われた通りのことをやって退けた。あれは、言外に北沢祐正と寝てこいと言われたも同然なのだ。仕事を終えると飲みに誘い、その後合意でホテルに連れ込んだことで一応の使命は果たした。あとは彼の機嫌次第である。自分を気に入るも気に入らないも祐正次第だが、とても気に入ってもらえたとは思えない。 そういえば、と思いついて、亮はそっとシーツを捲った。思い起こせば眩暈を感じそうなほどの甘美さで自分を包み込んだ身体とはいえ、知りもしない無謀な行為に、彼の身体が傷ついていないかと心配したからだ。 「……寒いんだけど」 寝入っているものと思っていた祐正の声が、くぐもって耳を打つ。 「すみません」 素直に謝ってから、亮はシーツを元通り祐正の身体に被せてやった。心配した通り、白いはずのシーツに、赤い液体が痛々しくこびりついていた。眠りたいわけではなく、起き上がれないだけなのかもしれない。 「レイプされたって本当だったんですか」 「つまんないこと言い出したのはおまえじゃねーか。嘘も本当もあるかよ」 咥えた煙草を吹かしている合間に、思いついた問いをそのまま口にする。デリカシーなど欠片もありはしない問いかけに、やはり祐正はくぐもった声で応えた。否定もせず肯定もしない。曖昧な返答に、亮は話を変えた。 「……どうして俺と寝たんですか」 「おまえ、社長に言われたんだろ。俺に取り入ってこいって」 自分なんかより長く業界の水に浸かっている祐正には、そんなことまでお見通しなのだ。今度は亮が黙り込む番だった。 「……俺も、おまえのところの社長には借りがあんの。乗っかっても、そう悪い話じゃない」 吐息のように吐き出して、祐正は心地好い体勢を探すように身じろぎした。シーツが僅かに下がって肩が露になる。それを持ち上げて直してやりながら、亮はまた問いを重ねた。 「北沢さん、痛くありませんか。……血が、出ていた」 吐息だけで笑う音がする。そんなことを訊くなんて馬鹿じゃないかと、嘲られているのだ。構わず、亮は静かに口を開いた。 「俺の彼女もレイプされました」 ほんの微かに反応して、祐正の肩が揺れた。唐突に選んだ不自然な話題に内心首を傾げながら、亮は伸びた灰を灰皿に落とす。今までのどの話よりも、不似合いで詰まらない話なのに、何の関係もない話なのに、なぜ今この口を突いて出てくるのだろう。 「彼女は黙って俺の前から姿を消しました。あんまり腹が立って、悲しくて、……気が付いたら社長のヒモにまで成り下がっていた。――あなたの言う通り、俺はセックスが嫌いなんだと思う」 強姦されたと告白を受けた後、彼女の身体を一度だけ抱いた。可哀想なくらいに強張って、凍り付いて、抱き返してもこなかった身体を思い出す。それが最後だった。そうさせたのが男という性だと思うと、自ずから湧き上がる情欲にさえ嫌悪した。なのに泣きたいくらいの官能を齎した、たった一度のセックスだった。 「……すみませんでした」 思えば、そのときの彼女と、祐正の反応が似ていたような気もする。だから、まさかと思ってしまったのだ。気のせいかもしれない、それでもまさか、万に一つでも。――万にひとつでも。 「言っただろ。借りがあるって。――これっきりじゃないんだろ?」 不自然に強い声音で背を向けたまま祐正が告げる。強い、なのに、震えた声で。 「俺が、おまえに力をやる。そうすればおまえの社長は満足するんだろ。満足させた分はきっちり返してもらう。俺は俺のためにしか動かない。もう、二度と謝るなよ――」 天才でも奇才でも何でもいい。ゲイ。震えた背中。レイプ。強張った頬。凍り付いた表情、柔らかな肉。そのどれもが彼に関する真実で、なのに、曖昧で確かではない。 「――惨めになる」 「北沢さん……」 彼は応えない。顔を見せないように背を向けているのに、なぜかその背中が泣いているような、そんな気がした。 まさかと思う。 けれど、泣いているんですか。 そうとは聞けず、亮はそっと手を伸ばした。色の抜けた髪に覆われた頬に触れると、指に感じた思わぬ冷たさに驚いて、掌を引き戻してしまいそうになる。濡れた感触が皮膚から伝わった。これを涙と呼ぶのなら泣いている。彼は確かに泣いているのだ。 「……祐正、さん」 亮には亮の考えがあり、祐正には祐正の考えがある。それが何かは知らないがお互い納得ずくの行為はずで、泣かれる覚えなどありはしない。なのに痛むのはなぜだろう。彼が泣いてしまうくらい、彼の胸を痛ませているのは。そして自分の胸を痛ませているものの正体は。 それは、愛なんて囁いたらきっと壊れてしまうやわらかな。 |
||
|