 溶かして / ヘタリア(プロイセン) 溶かして / ヘタリア(プロイセン)
|
|
何をしてるの、そう云う男の声が少し震えているのを見逃せなかった。 溶かして 男はもう一度何をしているのと云った。 それは置いてきた子供の言葉遣いに似ている。尤も、子供はそんな言葉づかいはもうしていないはずだが。プロイセンは振り向いて「帰る準備だ」と告げる。 「帰る場所なんてあったの?」 「――望まれた場所に帰るだけだ。」 「生まれ故郷でもないのに。」 男が云うように、プロイセンの生まれ故郷は帰ろうとする場所から離れている。むしろ男のほうが近いだろう。 それでも、ドイツの心がプロイセンを求めている。プロイセンには分かるのだ、戦後復興して経済的にも世界のトップクラスに立ち始めたドイツは今、故郷を求めている。生まれ故郷に住む原住民から名前をつけたといえども、プロイセンの本質はドイツの原点であった。 歴史を誇るイギリスや文化を誇るフランスに囲まれたドイツにとって、原点さえも辿れなくなるのは辛いのだろう。尤も、世界的な視点から見れば欧州の歴史など最近の事に過ぎないが。 「君を一度は否定したのに?」 「可哀そうなことを云ってやるなよ。誰だって刷り込まれたらそう思ってしまうだろ。」 「本当にそうだと思うの?」 プロイセンはちらりと後ろを振り返るものの、直ぐに旅行鞄に向き直り衣類を詰め込んでいった。四半世紀の間に手に入れたものはどうしようか、多少の愛着は湧いている。けれど、これらを持っていくのはどうであろう、ドイツはきっと良い顔をしないに違いない。そして彼ははっきりとプロイセンにその事を告げるだろう。 昔から意見をはっきりと云うし、そう躾けたのはプロイセン自身だ。なのにそれが辛いと思うのは――嗚呼、どうしたことだろう! 「第一、ここにはもう俺の居場所はない。」 「それでも君の生まれ故郷だよ。」 「そうだ、俺の生まれ故郷だ。だけど俺のものが何一つ残ってなくて景色さえも変わってしまった場所を、生まれ故郷という言葉だけで騙すのは限界がある。」 カタン、という音がしてプロイセンは振り返った。ドアの傍に立っていた男は、ゆったりとした足取りで部屋に入ってきてプロイセンの目の前に立った。しゃがんでいるプロイセンに目を合わせるように男は腰をおろす。 「君が望んだのに。」 触れてくる、と思った掌は空を彷徨って旅行鞄に置かれた。 「君も望んだじゃない。生きたいからって、そう望んだじゃない。ただの居候じゃなくて、昔みたいに国として成立してなくても自分の意思で生きていたいんだって。」 「そんなことも云ったっけな。」 「云ったよ。君は裏切りが得意だもんね。約束を反故にするのなんて簡単か」 「お前が云うなよ。第一、約束なんてしていない」 プロイセンがそう云うと、男は笑って「それもそうか。」と云った。四半世紀も共にいたものの、プロイセンには男がどんな実態をもっているのか更に分からなくなった。それでも、別れ際だと思うとそんな鈍重さも多少は愛らしくも見える。隣に男がいるとプロイセンは相変わらず身震いしてしまうことがある。 どうも、あの二回目の大戦であった冬将軍を思い出してしまうせいらしい。男の家に用意された部屋に住むようになってからは、冬将軍とも会う事もあった。彼は男を大事そうに守る。彼らのお互いの感情が愛憎でまみれていることに最初は反吐を覚えた。だが、自然にあれほど思われるというのはきっと素晴らしいことなのだろう。 「それに、」 「なに?」 「ドイツがようやく帰ってこいって云ってくれたんだ。もう俺は何もせずにただあいつの傍にいたい」 ドイツの名を口にした事に、男はピクリと反応した。そうして二コリと男は笑った。 「君がそんなに彼を思っているのに、彼は君の事はずっとお荷物としか思ってなかったよね。いや、彼だけじゃないか。ヨーロッパの皆が君を捨ててしまいたいと思ってた。他の地域の皆は君を忘れていっている。可哀そうだね。」 「・・・お前だって、皆に疎外されてんじゃねえか!ソビエト!」 「そうだね、でも僕の場合はロシアが僕を愛してくれている。ずっとずっと彼は僕を愛してくれる。でも、君はそんなロシアからもお荷物と思われている」 「うるせえよ!」 「僕がいくら批判されても怒らないのは、ロシアやベラルーシが愛してくれているから。でも、君は怒るってことは君は誰からも愛されてないんだね。」 ねえ、と男は云った。 「早く出て行ってよ。僕も君が嫌いなんだ」 今さら報いが来たのだと思う。 自分の力を誇示して他国を平気で傷つけてきたその報いだ、それが全て己が生き残るための手段だったとしても。 東独になってもソビエトのところに住んでいた他の国よりもマシだったという自負がある、例え良い成績を残すために五輪で選手に薬をやらせてしまったとはいえ。 結局、残ったのはすべて薄っぺらいモノばかりのような気がする。 今は敬愛する大王の宮殿に足を運んでも、心が何の反応も示さない。ただひたすらに傷つかないようにと殻に閉じこもっている。ドイツがプロイセンを招いたとはいえ、一度はプロイセンを全否定した事実は消えない。 (兄さんなんか大嫌いだ!) あの頃は、この子供が傷ついて立ち上がられなくなるならば、とその言葉を全て受け止めてソビエトの家で暮らすことも承諾した。ドイツは、プロイセンが生涯で仕上げた最後の作品といってもいい。その作品が壊れぬように、また評価をもらえるようにするには負の部分を全て引き受けてしまえばよかった。 ソビエトのあの甘ったるい声――男は、君は優秀だねえ、と外でもプロイセンを自慢するような口調でいたけれどその実、東独であるプロイセンに情をかけることは一度もなかった。それが国の常識だと分かっていても、時には嬉しくもなり荒んだりもした。 それでも、戦争をした国々が仲を直したり、罵倒しつつもお互いを認める仲になったりするのだとしたら、己にもその権利はあるのではないだろうか、と列車の中でプロイセンは考えていた。 ポーランドやリトアニアはどうだろう、彼らに恨まれる謂れはあるけれど、こちらだって恨みはあるのだ。それらを解消して――できるわけもないか。解消するにはあまりにも複雑な気持ちがよぎってしまう。様々な国の顔が浮かんでは消えた。 だが、それらの国々が自分に思いを巡らすことがあるのだろうか、と思ってプロイセンは自嘲気味に笑った。実際には半世紀も前に名前を亡くした国だ、いやそれ以前からプロイセンの存在はドイツにとって代わられていたのだ。誰が一体こんな自分を思い出すというのだろう。 そう考えると、ドイツはやはり肉親なのだと思わざるを得ない。東独が事実上、ドイツに吸い込まれてからドイツは必死で東側の開発に取り組んだ、その代表がベルリンだ。その代わり多大なる借金を負ってしまったが。それらが一段落ついたからこそ、ドイツはカリーニングラードにぽつんと置かれていたプロイセンを引き寄せることにしたに違いない。 (あいつだけは、俺を、見捨てない) 本当に? と囁いてくる心の声を無視して、プロイセンは次の駅で降りるために旅行鞄を手に取った。 (たった一人でいい、あいつだけは、見捨てはしない。) 住所の書かれた紙を握りしめたプロイセンは、こくりと唾を飲み込んでベルリンの駅に降り立った。 |
|
written by 吉沢(路地裏) 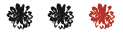 |