 歌は何う読む 心のいとを 声と言葉で 綾に織る / 歴史創作(細川忠興+忠隆) 歌は何う読む 心のいとを 声と言葉で 綾に織る / 歴史創作(細川忠興+忠隆) |
|
その人は随分と雰囲気を変えていた。二十六年目にして、ようやく体面を果たした二人はぽつぽつと話し出す。 慶長五年、関ヶ原での合戦前に石田三成は大坂屋敷に身を置く大名の妻子を人質にとろうとした。予想していた大名たちは各自家臣に指示を与えていたが、細川忠興は人質に取られるぐらいなら、と妻である玉子に死を命じていた。細川屋敷を襲撃された折、彼女はその言葉を守った。 だが、隣家に宇喜多家という親類がいたため、忠興の嫡男・忠隆の妻である千世は宇喜多秀家の妻であり、彼女の妹である豪のいる宇喜多屋敷に逃げ込んだ。 戦後、これが問題になった。 政権における前田家の危なっかしい位置と細川家の体裁を思い、忠興は千代を実家である前田家に送り返せと忠隆に命じた。第一、何故玉子と行動をともにしなかったのか理解できぬ、と。 しかし忠隆は承知しなかった。他家はその家臣どもに脱出を命じている――私には父上が母上に自殺を申しつけられたこと自体、不満であり千代の判断は間違っていない――。 二人の意見は遂に交わらず、忠興は新領地である豊前には忠隆を連れず遂には廃嫡した。結局は、三男である忠利が二代目豊前小倉藩細川家の領主となっている。その後、二十数年間、二人は親交を完全に断っていた。だが、六年前に忠興が一度忠隆を訪ねた事によってそのぎすぎすとした仲も若干和らいだようにも思える。 今日、忠隆が子を連れて細川家の新領地である肥後熊本藩にある忠興の隠居地に訪れたのは、正式な形で和解するためであった。既にそれらは済み、二人は雑談をし始めていた。 「変わりのう過ごしておったか。」 「ええ。父上も御達者そうでなによりでござる。」 「京では相変わらず歌を詠んでいると聞いたが」 忠隆はわずかに目じりを下げて笑う、忠興が彼の笑い顔を見たのは実に二十数年ぶりだ。 それどころか顔を合わせる事もなかった。彼は大名特有の雰囲気は持ち合わせていなかったが、かつて硝煙のにおいを嗅いだ頃の精悍な顔つきはまだ残っているようにも感じられる。尤も忠興自身も戦場から離れて久しく、元亀天正の時代の中を生きたということは一種の伝説味さえ帯び始めている。 「お祖父様に鍛えられましたし、私も細川の者だったというべきかその道にも明るいようです」 「そうだな、お前は文武共に秀でていたから父上に気に入られていた。」 「子らにはお会いしましたか。」 「いや、今日はまだだ。」 忠隆は不思議な雰囲気を纏っていた。二十六年という年月は忠興を衰えさせ、忠隆を熟成させた。忠隆は暗愚だったわけではない。それどころか忠興も口にした通り忠隆は文武共に秀でており、彼にとって祖父にあたる幽斎にはその才を愛されていた。明智家と細川家という才覚に富んだ家柄の血をひくだけのことあって細川家の当主として彼は申し分なかった。 だが、関ヶ原の合戦以前から忠興と忠隆にぎくしゃくとしたところがなかったとは云えないことも事実だった。 季節の話や世の動きをとりとめもなく話しているところに、茶が運ばれてきた。 その者が忠隆に小さな声で囁く。 「徳たちが、これよりこちらに参るそうです。」 「悪いが、もう少し後にはできまいか。」 「・・・父上?」 「今しばらく話したい。」 わずかに忠興を見つめた忠隆は、では半刻後に、と先程の女中に申しつけた。 「忠隆、」 「なんでしょう。」 「こちらに、肥後に来てはいかがか。わしの隠居地である八代に住めば本家には迷惑はかからぬであろうし、それに肥後は暖かい。」 忠隆はしばし口を閉ざしたままでいたが、しかし「申し訳ございませんが、私にはできかねます」と頭を下げながら云った。 「何故?」 「忠利には気を遣わせてしまいましたし、お祖父さまには随分とお世話になりました。こちらにきてしまえばお祖父さまへの線香を絶やす事になります。それに京は幼少から馴染み深いところ、京のほうが私には水があっております故」 忠興はそうだな、と答えて、それ以上は追及しなかった。どんなにたくさんの言葉で云い募っても彼は結局固辞してしまうだろう、結果の見えている問答など忠興はしたくなかった。 「私は良い弟を持ちました。」 と、忠隆は唐突に別のことを口にした。 「皆、それぞれの立場を果たせたと思っております。」 「――儂も立派な子を持てて幸せじゃ。」 忠興は忠隆の手を取った。忠隆はその手を振り払わない。何かを口にしかけた忠興はゆっくりと口を閉じた。忠孝も何も云わなかった。 生温い雰囲気に二人は戸惑った、かつてはこんな雰囲気は二人の間には存在しなかったのだ。 許すか許さぬか、許しを請うか謝罪をするか――しかし、今はどんな言葉も意味足らずで余計なものとしかならないだろう、二人の間に深い溝が横たわっている事をお互いに知っている。それ故に求めるのか、それ故に拒絶するのか。 言葉を選んでは捨て、互いの心理を慮って届かない距離に小さなしかし絶対的な絶望を覚える。それらを全て隠すかのように忠興は手を握り続けた。 「――そろそろ、徳らを呼ぶかの。」 「そうですね。あれらは千世の子にございます。」 「達者でおられるか。」 「数年前に亡くなりました。しかし、よくつくしてくれましたし、再嫁してからも達者で暮らしていたようです。」 「そうか。」 千世は細川家とは離縁させていたが、忠隆は幽斎が亡くなるまでは彼女をその手元に置いていたのだ。細川家は本家ではない場合、姓を長岡と名乗る。長岡忠隆はあれからも千世と共に暮らしていた。 忠興は、自身が玉子を匿った時のことを思い出していた。 「父上、」 「なんだ。」 遠くからはしゃいだ雰囲気が近づいてくる、徳たちが廊下を小走りにやってきているのだろう。 「ご無理をなされませぬように。お身体を大切にしてください。」 その時、襖の外から声が掛かり、忠隆の子である徳らが来たことを告げた。 お題提供元:モノカキさんに都々逸五十五のお題 |
|
written by 吉沢(路地裏) 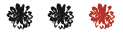 |