 汝、隣人を愛せよ / 涼宮ハルヒの憂鬱 小泉+キョン 汝、隣人を愛せよ / 涼宮ハルヒの憂鬱 小泉+キョン |
|
窓からわずかに風が入ってくる。季節は秋から冬へ移り変わろうとしていた。 古泉はいつもよりHRが早く終わったため、人影の少ない廊下をゆったりとした足取りで歩いていく。誰もいないだろうと思っていた部室には人影があった。解放された窓からは冷たいというよりは涼しい風が入り込んでいる。 電気のスイッチを入れて古泉は「お早いですね」と声をかけた。 「HRがなくなったからな」 「涼宮さんは?」 「あいつは掃除当番で遅れる。」 「そうですか。まだ皆さん来られる様子がありませんから、オセロでもしませんか?」 椅子に座ってぼんやりとしていた青年はわずかに口角をあげた。 汝、隣人を愛せよ 女性三人はなかなか来なかった。 今日は特に連絡はなかったんですが、と古泉が呟くと何か面白いものでも見つけたんじゃないかと彼は答えて白を黒へと三つほどひっくり返した。古泉はオセロ盤を見つめる。黒は白よりも多く優勢だった。 古泉は、彼にはどんなゲームをやっても勝てないが、不思議なことにその事に対して何も感じなかった。 「あなたは神様と云われて何を思いついていましたか、」 「は?」 「彼女が神であると僕たちから聞かされるまで。」 彼は「ああ、」と相槌を打ったあと、なんだったかなと思いだすように天井を眺める。古泉はパチンパチンと軽い音を立てて黒石を二つひっくり返す。彼は、オセロ盤をちらりと見やって「宗教を特に気にしたことはなかったな」と云った。 現代のこの国にあっては、特定の宗教上の髪を信じるという観念をもたない人間は圧倒的に多い。彼もそういう一人であろう。 「少なくとも何かしてくれる存在だとは思ってなかったな。」 「でも神頼みという言葉もあるでしょう。」 「あれは、言葉のあやだろ。本当に神様に縋りつく人間は少ないと思うぞ・・・なあ、古泉。」 「なんですか。」 古泉、と呼びかけられて目線を合わせたとたん、彼は白石を黒石へと5つひっくり返した。申し訳なさげにオセロ盤に残っている白石が哀れにも見えるが勝負はついていない。古泉は手元から白石を取り出して盤上を眺めた。だが、正面から視線を感じて顔を上げた。 僅かに眉が寄せられており、彼はあまり機嫌がよさそうではなかった。古泉はもう一度なんですか、と告げた。 「恐がるなよ。」 「何を、」 「何をなんて俺は知らん。あいつは神かもしれんが、でも、ただの人間で女の子だ。必要以上に恐がるのはやめろ。」 でも、と古泉は呟いた。恐いでしょう、いつか厭きられて要らないと思われるのは――。 彼はその言葉とともに置かれた白石を見つめ、暫くしてから古泉を見上げるようにして見やった。先程よりも寄せられた眉に彼はもう怒っているとしか思われなかった。 「覚えとけ、古泉。そういうことを云う奴や他人に厭きて要らないと思う奴をクソ野郎っていうんだ。」 彼が打った黒石によって縦、横、ナナメと一気に黒石に変えられて最早巻き返しは不可能と思われるところまで追い詰められた。なおかつ空いているカ所も少ない。僕の負けですね、と古泉が云うと「続けろよ、まだ空いてるだろ」と返ってきた。 古泉は、そろりと白石を手元から一つ取り上げて、しばしオセロ盤上を眺めてから打った。 「・・・訂正する。」 「え?」 「そういう事をグズグズいつまでも考えたり他人をいらないと思って消そうとするやつがクソ野郎だ・・・思うまでは仕方ない、よな。」 「・・・僕も神様は信じていなかったんです。彼女を知るまで」 彼はちらりと古泉を見て、それから黒石で升を一つ埋めていく。白石が一つ、申し訳なさそうに黒にひっくり返る。何時の間にか風がやんでいた。それでも、肌寒さを感じたのか古泉は窓を閉めに席を立った。 「涼宮さんたちは外にいるみたいですよ。」 「はあ、」と手招きされた彼は立ち上がる。なるほどハルヒを筆頭したSOS団の女性三人が他の生徒と混じって何かしているようだった。ハルヒが中心だから、どうせろくでもない事にちがいない、と古泉は彼が思っている事を手に取るように分かった。だが、そうした彼女らの行動を見ていると本当にただの高校生のように見えた。 「あいつは、情のない奴じゃない。わがままだけどな。」 古泉は静かに笑って「知ってますよ」と答えた。 「彼女たちのところへ行きましょうか。」 その言葉と同時に彼の携帯電話が鳴り響く。名乗る前に鼓膜を破るような大音量が携帯電話から漏れてくる。 内容には彼に改めて確認する事もないだろう、古泉はわずかに笑みをこぼしながらオセロの石を丁寧に両サイドに戻していく。 「分かったから怒鳴るな!古泉?ここにいる。そんなすぐに行けるわけなっ・・・ったく。勝手に切りやがった。おい、聞こえたろ。神様からのお呼び出しだ。」 「僕もですか?」 「当たり前だ」 「わざわざ聞くな、」 彼は乱雑な手つきで残りの石を戻すと、三分で行かねえとまた何か云い出すから急ぐぞと大して急ぐ様子でもない口調で云った。 オセロを片づけた二人は鍵を閉めて部室を出た。 (涼宮ハルヒを抑え込む鍵――) しかし、それはまた開け放つものでもある。古泉はちらりと彼を見て、小さく息を吐きだした。 |
|
written by 吉沢(路地裏) 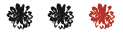 |